サ道(サウナ道)と瞑想道の共通している点
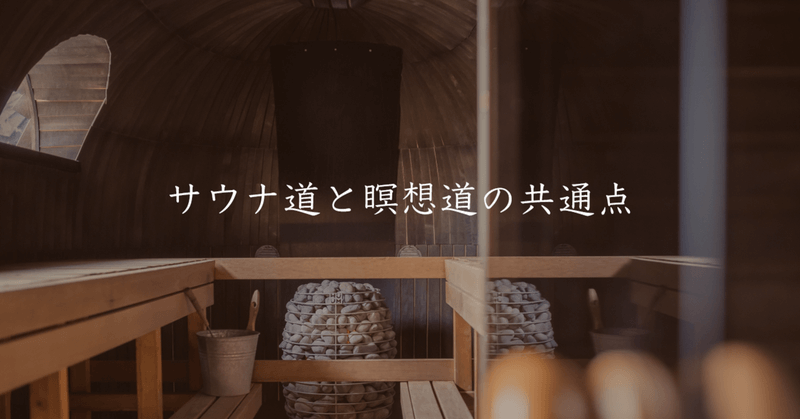
「サ道」「サウナー」「ととのう」
近所のサウナに入ることができる施設をネットで検索していて、本当にごく最近「サ道」「サウナー」「ととのう」などの用語を偶然に知りました。
ワタシはテレビ、雑誌、新聞などはほとんど見たり、読んだりしないので、「サ道」という漫画が流行ってそれがテレビで去年実写化されて「サウナ」が割と流行っているということを全く知りませんでした。
このサウナー用語で「ととのう」という言葉の意味を知ったとき、自分が以前からサウナや温泉に入るときに瞑想状態に入るために自然とやっていた方法と殆ど同じだったので、とても面白いなぁと思いました。
「ととのう」状態と「瞑想」状態の共通点
それと同時に「ととのう」状態と 「瞑想」の状態とけっこう共通している部分があるなと感じました。
ちなみに「サウナー」というのは「サウナを愛し、サウナ浴を日常的に楽しんでいる愛好家の方々のこと」という意味で、 「ととのう」というのは 「サウナ室〜水風呂〜休憩を 3 回程度くりかえすことで得られる、多幸感、一種のトランス状態」のような意味らしいです。
「サ道」という漫画の中で推奨しているサウナの入り方というのは、 「① サウナ室に入る → ② 水風呂に入る → ③ 外気浴(外気にあたれるスペースで休憩すること)」
を 1 セットとして、何セットか繰り返すというもの。サウナ室にいる時間は「何分間いなければならない」というものではなく、「水風呂に入りたいな」と思えるくらいの時間がちょうどいいのだとか。
水風呂を出た後、外気浴をしているとリラックス状態が極限を迎え多幸感や恍惚感を覚えることがあり、この状態を「サウナ―」は「ととのう」と呼んでいて、これは心や体の調和がとれるという意味の「整う」と、必要なものがそろう「調う」という 2 つの意味からつくられた言葉のようです。
国際医療福祉大学病院の内科医、一石英一郎さんによると「ととのう」状態は、「瞑想」に近いものだそうです。高温のサウナ室や冷たい水風呂では緊張状態へと導く「交感神経」が優位になり、外気浴の間は神経のスイッチが切り替わって、リラックス状態へと導く「副交感神経」が優位になります。その際に「幸せホルモン」である、「オキトキシン」や「セロトニン」の分泌が促され、落ち着いた気分、すなわち「瞑想」に近い状態になるとか。
「サウナで「ととのう(整う、調う)」とは? | ハルメク WEB」から引用 https://halmek.co.jp/qa/420
現代人のためにデザインされたアクティブ・メディテーションとは?
ワタシは瞑想がとても好きで 20 年くらい瞑想をこれまで続けてきて、どうやったら日常生活の 24 時間を瞑想的な状態で過ごすためにイロイロな瞑想法を試してきました。
瞑想法の中で一番長く愛好して続けてきたのが、現代人のためにデザインされたアクティブ・メディテーションという瞑想法です。
このアクティブ・メディテーションというのは 20 世紀最大の精神的教師、神秘家の Osho によってつくられたもので、様々な種類があります。その主な特徴として
「動(アクティブ)≒ 緊張(テンション)」 「静(パッシブ)≒ 弛緩(リラクゼーション)」
のパートに分かれている所です。
これが伝統的な静かに座るだけのヴィパッサナー瞑想などの瞑想法と違う所です。例えばアクティブ・メディテーションの中にダイナミック・メディテーションという代表的な瞑想法があって、この瞑想法の最初の「動(アクティブ)≒ 緊張(テンション)」のステージは簡単に説明すると以下のようです。
① 混沌とした速く、深い呼吸 10 分間おこなう。 ↓ ② 日常的に抑圧してしまった感情をすべて解放する。 内側にある狂気すべてを表現する。叫びたかったら叫び、泣きたかったら泣き、飛び跳ねたかったら飛び跳ね、踊りたかったら踊る。 ↓ ③ 10 分間、ジャンプし、 マントラ「フー」「フウッ」を叫ぶ。命が懸かっているかのようにエネルギーをトータルに注ぐ。
詳しいダイナミック瞑想の説明はこちらをご覧ください。
次に「静(パッシブ)≒ 弛緩(リラクゼーション)」 のステージは、ストップ。15 分間の完全な静止して、静寂と共にあります。
厳密に言うと、最後のステージがあって 15 分間のダンスを通して、「いまここ」で感じているものを表現し祝福します。
第 1、第 2、第 3 ステージを呼吸とカラダを精一杯動かして最大限アクティブな状態になることを通じて、カラダの中に滞っていたエネルギーが動き始めます。
そして第 3 ステージの突然のストップで、突然静寂の中に投げ込まれます。
それまでの「動(アクティブ)≒ 緊張(テンション)」のステージから打って変わって、「静(パッシブ)≒ 弛緩(リラクゼーション)」の状態に突然ギアチェンジがなされることで、「動き」と「静けさ」のギャップが際立ちます。
そのギャップを通じて、自然といつも以上に「静けさ」を感じることができ、自分自身の中心にある空だったり、無を味わったり、それとひとつになるのを感じるかもしれません。
最後の祝祭の踊りを通じて、エネルギーの「動き」と「静けさ」のスペースが統合され、行為と非行為の 融合が起こります。
「動 ≒ 緊張」と「静 ≒ 弛緩」の両極のプロセスがきっかけ
この「動(アクティブ)≒ 緊張(テンション)」と「静(パッシブ)≒ 弛緩(リラクゼーション)」のステージを経ることで、自然と瞑想の状態が生まれる感じがサウナ道で紹介されている下の「ととのう」方法と共通していると思ったのです。
「① サウナ室に入る → ② 水風呂に入る → ③ 外気浴(外気にあたれるスペースで休憩すること)」
「ととのう」ことも「緊張」と「弛緩」を通して、 自然とおこること、あたえられること。
「瞑想」も同じように、上で紹介したような瞑想法の「動(アクティブ)≒ 緊張(テンション)」と「静(パッシブ)≒ 弛緩(リラクゼーション)」のステージを経て、 「瞑想」や「悟り」が自然とおこること、あたえられること だと感じます。
コツはただ何もしないで寛ぎ、そしてただ待つことソノモノを楽しむこと。
大切なのは「ととのう」ことを直接的に「Do する」ことはできなくて、 サウナ浴と水浴や外気浴でただ何もしないで寛ぐことを通じて、「ととのう」ことが自然と「happen おこる」ことをゆるすこと 或いは「ととのう」状態(Be )に自然に還っていくこと。
その状態を過剰に期待したり、やり過ぎ「Overdo」てしまったら、 その状態から離れてしまう。
コツはただ何もしないで寛ぎ、そしてただ待つことソノモノを楽しむこと。
「瞑想」にも似たようなことが言えて、 「瞑想」も直接的に「Do する」ことはできなくて、瞑想法を通じて自然と瞑想状態が「happen おこること」をゆるしていく或いは元々本来「Be あった」状態に還っていく。
だからハイの状態を求めたり、悟りを求めたり、クンダリーニの上昇や第三の目の覚醒を求め過ぎたりすると、かえって逆に元々本来あるがままで自然にすべて備わっている状態から離れてしまう。
鍵は純粋に何もしないで寛ぎ、静けさの中にあることをシンプルにただ味わい楽しむこと。
ワタシの敬愛する道元禅師は言っています。
「悟りを求めて坐禅をするのではない」とは、「坐禅そのものが悟りである」
このシンプルな言葉がすべてを簡潔に表わしていると思います。
サ道と瞑想道のクロスオーバー・交差点
今回の記事ではサウナーには瞑想道の素晴らしさを知ってもらい、より深くととのうことを楽しんでもらえたらと思って、瞑想の話を少し書きました。
またメディテーター(瞑想をする人)にはサウナ道というものがあることを知ってもらい、より瞑想をサウナ道を通じて深め楽しんでもらえたらと思い サ道(サウナ道)について少し書きました。
ワタシが 6,7 年前から瞑想の状態に入るために、サウナや温泉で自然とやっていた方法が「サ道」「ととのう」という言葉で表現されていて、サウナがかなり流行っていることを最近になって初めて知り、驚きました。
また多くの人が心身と意識をととのえることだったり、ひとり自分自身と向き合うことだったり、フローやゾーンに入ることを潜在的に求めているのだなとあらためて感じて、嬉しく思いました。
信州の森の中にやはりサウナ小屋をつくりたい!
信州の森の中にやはりサウナ小屋をつくりたい!
奥深い山の中で 冬でもサウナ小屋でととのってから、 瞑想ホール(小屋)で瞑想できる環境をまずは 準備して、整えていけたらと思っています。
現在信州聖山の 4 千坪の森の中に実際に住みながら、 持続可能な“懐かしい未来”に向けて生きる人々のための スペースの準備をしています。